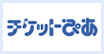過去のオススメ商品につきましてはリンク先の販売サイトで価格変更や販売が終了している場合がございます。
プレゼンターのこれまでのオススメ!PickUP
1
2017.11.18
戦争交響楽 音楽家たちの第二次世界大戦 (朝日新書) 新書 中川右介著
972円
久しぶりに私がお勧めする絶版でない本・・・・どころか最新刊です。(2016年4月刊)
8月の日本は、戦争について考える月です。この記事がアップされる8月6日・・OTTAVAサロンコンサート 本田聖嗣定「季」演奏会の当日・・・はもちろん、広島の原爆平和祈念の日、9日は長崎の原爆忌、そして15日は終戦記念日・・と昭和20年の惨禍の数々に思いをはせる月です。私は、昭和生まれなので、学校の先生などに、実際に戦争をくぐりぬけた方が多く、そういう方たちから直接うかがった「あの日は・・・・だった」という体験談が、いまだに強烈に記憶に残っており、自分が生まれるはるかに前のことではありますが、「準体験」的な記憶として、刻まれています。多くの直接体験者が鬼籍に入られた今、どのように自分より下の世代に伝えてゆくか・・というのは課題だと思っています。
欧米だけでなく東洋の国々も巻き込んだ未曽有の世界戦争である第2次世界大戦は、人々の人生を強烈に狂わせました。芸術に介入し、音楽能力の高いユダヤの人々を迫害したナチス政権・・・「画家志望」のヒトラーと、「小説家志望」のゲッベルス、彼ら「三流芸術家」が「一流芸術家」を政治の名のもとに、行動を規制した、という記述が本書には出てきますが、なかなか興味深い分析です・・・によって、特に本国ドイツの音楽家たちが人生を狂わされ、苦悩し、その中でも活躍を新天地に求めたりする様子が淡々と描かれています。1冊の新書に収めるために内容量は限界がありますし、ドイツだけでなく、世界中の人々の人生がゆがめられたわけですから物足りない点があるかもしれませんが、時系列で、改めて、あの時代の迫りくる恐怖・・・・・戦争とは空襲や戦闘だけが恐ろしいのではなく、「戦時下政治による一般の人々への圧迫」が何より怖い、というのが経験者からうかがったのとも重なります・・・・・を追体験できます。
この本で、私個人的には、「戦争交響楽」とか「夏の祭典」とか「戦争の情景」といったように、さりげなくクラシックパロディーな章タイトルがつけられているところと、知ってはいても、あらためて行動をたどると、フルトヴェングラーの見事な政治音痴ぶりに「音楽以外は音痴なのね」と嘆息したり、・・・等々で楽しみましたが、8月に読んで、あの時代を思い、考え返してみたい一冊となりました。
8月の日本は、戦争について考える月です。この記事がアップされる8月6日・・OTTAVAサロンコンサート 本田聖嗣定「季」演奏会の当日・・・はもちろん、広島の原爆平和祈念の日、9日は長崎の原爆忌、そして15日は終戦記念日・・と昭和20年の惨禍の数々に思いをはせる月です。私は、昭和生まれなので、学校の先生などに、実際に戦争をくぐりぬけた方が多く、そういう方たちから直接うかがった「あの日は・・・・だった」という体験談が、いまだに強烈に記憶に残っており、自分が生まれるはるかに前のことではありますが、「準体験」的な記憶として、刻まれています。多くの直接体験者が鬼籍に入られた今、どのように自分より下の世代に伝えてゆくか・・というのは課題だと思っています。
欧米だけでなく東洋の国々も巻き込んだ未曽有の世界戦争である第2次世界大戦は、人々の人生を強烈に狂わせました。芸術に介入し、音楽能力の高いユダヤの人々を迫害したナチス政権・・・「画家志望」のヒトラーと、「小説家志望」のゲッベルス、彼ら「三流芸術家」が「一流芸術家」を政治の名のもとに、行動を規制した、という記述が本書には出てきますが、なかなか興味深い分析です・・・によって、特に本国ドイツの音楽家たちが人生を狂わされ、苦悩し、その中でも活躍を新天地に求めたりする様子が淡々と描かれています。1冊の新書に収めるために内容量は限界がありますし、ドイツだけでなく、世界中の人々の人生がゆがめられたわけですから物足りない点があるかもしれませんが、時系列で、改めて、あの時代の迫りくる恐怖・・・・・戦争とは空襲や戦闘だけが恐ろしいのではなく、「戦時下政治による一般の人々への圧迫」が何より怖い、というのが経験者からうかがったのとも重なります・・・・・を追体験できます。
この本で、私個人的には、「戦争交響楽」とか「夏の祭典」とか「戦争の情景」といったように、さりげなくクラシックパロディーな章タイトルがつけられているところと、知ってはいても、あらためて行動をたどると、フルトヴェングラーの見事な政治音痴ぶりに「音楽以外は音痴なのね」と嘆息したり、・・・等々で楽しみましたが、8月に読んで、あの時代を思い、考え返してみたい一冊となりました。

本田聖嗣
2017.11.18
ブラームス:弦楽五重奏曲1&2 アマデウス弦楽四重奏団、セシル・アロノヴィッツ
1,393円
長期予報によると今年は、残暑も厳しく、長く暑い夏になるとのこと。なんだかこの情報だけで気が重くなっちゃいますよね。。こんな時は、耳から涼を取ってみてはいかがでしょうか?ということで今回は、日本の夏に音の涼風を届けてくれるCDをピックアップ。(と言いつつ、実のところ、このアルバムを取り上げたのは、今日がゾロ目の8月8日なのでOp.88の作品を、というくだらない理由からなのですがw)
ブラームスが、1882年の初夏に、オーストリアの豊かな緑と清らかな水にあふれた保養地、バート・イシュルで書き上げたという『弦楽五重奏曲 第1番 Op.88』は、まるで彼の地に吹くさわやかな風を音楽にしたかのような印象を聴く者に与える名作です。
ブラームス自身もかなり気に入っていたようで、出版社のジムロックに宛てた手紙に「あなたは今までに私からこんなに美しい曲を受け取ったことはなかったでしょう。そして、ここ10年でこんな曲を出版したこともなかったでしょう」と綴っていたとか。わお、自信満々!
演奏はこの曲の定番の名演として名高い、セシル・アロノヴィッツとアマデウス弦楽四重奏団によるもので、カップリング曲は、『弦楽五重奏曲 第2番 Op.111』です。
夏の厳しい暑さを乗り切るためのアイテムとして、ぜひ♪
ブラームスが、1882年の初夏に、オーストリアの豊かな緑と清らかな水にあふれた保養地、バート・イシュルで書き上げたという『弦楽五重奏曲 第1番 Op.88』は、まるで彼の地に吹くさわやかな風を音楽にしたかのような印象を聴く者に与える名作です。
ブラームス自身もかなり気に入っていたようで、出版社のジムロックに宛てた手紙に「あなたは今までに私からこんなに美しい曲を受け取ったことはなかったでしょう。そして、ここ10年でこんな曲を出版したこともなかったでしょう」と綴っていたとか。わお、自信満々!
演奏はこの曲の定番の名演として名高い、セシル・アロノヴィッツとアマデウス弦楽四重奏団によるもので、カップリング曲は、『弦楽五重奏曲 第2番 Op.111』です。
夏の厳しい暑さを乗り切るためのアイテムとして、ぜひ♪

ゲレン大嶋
2017.06.28
音楽の歴史を物語として楽しく読ませてくれる好著です。いわゆる音楽学者ではなく、現役の作曲家によって書かれているという点も、見逃せません。
3,456円
梅雨の季節はOTTAVAを聴きながら、晴耕雨読・・といきたいところですが、最近の梅雨は激しく降ってしばらくそのあとは曇り・・のような雨量の少ない季節になっていますね。この本は、梅雨の時にも、またはそのあとヴァカンスにもっていくのにもおすすめの1冊。
OTTAVAファンならば、多少なりとも音楽史には興味がわくと思いますが、いわゆる音楽史本は記述も無味乾燥で、しかも量が多くて、イマイチ読み出せない・・という方にもおすすめです。ほかならぬ私が、音楽史を学び返したくて何度挫折したことか。中世の音楽からバロックに至らずに討ち死に・・してしまうのは、主に文体や無味乾燥な記述も原因です。
その点、この本はエミー賞受賞歴もあるオックスフォードに学んだイギリス人作曲家によって書かれている、というだけで興味をそそられます。実際に読んでみると、自らが作っているだけに、その快刀乱麻ぶりも見事。「技術的には、モーツァルトの音楽はハイドンのものとそう変わりはない。同じようなオーケストラを使っているし、和音もほぼ同じ、曲の構造にも大きな違いはない。ただ、モーツァルトには、神から授かったとしか思えないようなメロディづくりの才能があった。彼の作る曲は、メロディ自体が歌っている。他の誰が作った曲よりもそうだ。」などという、大胆な記述が出てきます。腰が引けた「研究者」にはこれは無理な記述でしょう。私は、「そして、ハイドンとモーツァルトでは人の驚かせ方がちょっと違う。ハイドンは情緒安定の中でのサプライズだが、モーツアルトはまず何よりも気まぐれに音楽を動かしてから仕掛ける・・・」などと付け加えたくなりますが、とにもかくにも著者グッドールは、このような大胆不敵な分析で、バッタバッタと西洋音楽史をなで斬りにします。
イギリス人、というのも利いていて、「プロヴァンスシリーズ」のピーター・メイルのように、「どちらかというと本場でないイギリス」から、欧州大陸を眺める、という斜に構えた記述もにやりとさせますし、同時に、「自国」であるイギリスの音楽にも愛情をもって記しています。この点だけでも、良質なイギリス音楽をよくお届けするOTTAVAファンにとっては、とっても買い!だと思います。私も、いわゆる一般的な音楽史に記述される「以外」のところの内容を興味深く読んでいます。
有史以来の音楽史は長いため、大著にならざるを得ませんが、この本は先史時代から現代のコンピューターが発達した時代まで網羅している割には、500ページ未満に収まっていますし、「消滅の危機にある」とされるクラシックファンにとっては、考えさせることの多い本でもあります。とにかく、従来のいわゆるクラシックに限った音楽史とは、大いに違う、一冊です。
ちなみに、原題はただ「The Story of Music」です。背表紙だけ見て理解してもらうために「音楽の進化史」と、内容に沿ってかなり意訳した訳者さんの気持ちもよくわかるのですが、読み終わってみると、まさに「音楽の物語」だったよなあ、と納得する、素敵な本なのです。
OTTAVAファンならば、多少なりとも音楽史には興味がわくと思いますが、いわゆる音楽史本は記述も無味乾燥で、しかも量が多くて、イマイチ読み出せない・・という方にもおすすめです。ほかならぬ私が、音楽史を学び返したくて何度挫折したことか。中世の音楽からバロックに至らずに討ち死に・・してしまうのは、主に文体や無味乾燥な記述も原因です。
その点、この本はエミー賞受賞歴もあるオックスフォードに学んだイギリス人作曲家によって書かれている、というだけで興味をそそられます。実際に読んでみると、自らが作っているだけに、その快刀乱麻ぶりも見事。「技術的には、モーツァルトの音楽はハイドンのものとそう変わりはない。同じようなオーケストラを使っているし、和音もほぼ同じ、曲の構造にも大きな違いはない。ただ、モーツァルトには、神から授かったとしか思えないようなメロディづくりの才能があった。彼の作る曲は、メロディ自体が歌っている。他の誰が作った曲よりもそうだ。」などという、大胆な記述が出てきます。腰が引けた「研究者」にはこれは無理な記述でしょう。私は、「そして、ハイドンとモーツァルトでは人の驚かせ方がちょっと違う。ハイドンは情緒安定の中でのサプライズだが、モーツアルトはまず何よりも気まぐれに音楽を動かしてから仕掛ける・・・」などと付け加えたくなりますが、とにもかくにも著者グッドールは、このような大胆不敵な分析で、バッタバッタと西洋音楽史をなで斬りにします。
イギリス人、というのも利いていて、「プロヴァンスシリーズ」のピーター・メイルのように、「どちらかというと本場でないイギリス」から、欧州大陸を眺める、という斜に構えた記述もにやりとさせますし、同時に、「自国」であるイギリスの音楽にも愛情をもって記しています。この点だけでも、良質なイギリス音楽をよくお届けするOTTAVAファンにとっては、とっても買い!だと思います。私も、いわゆる一般的な音楽史に記述される「以外」のところの内容を興味深く読んでいます。
有史以来の音楽史は長いため、大著にならざるを得ませんが、この本は先史時代から現代のコンピューターが発達した時代まで網羅している割には、500ページ未満に収まっていますし、「消滅の危機にある」とされるクラシックファンにとっては、考えさせることの多い本でもあります。とにかく、従来のいわゆるクラシックに限った音楽史とは、大いに違う、一冊です。
ちなみに、原題はただ「The Story of Music」です。背表紙だけ見て理解してもらうために「音楽の進化史」と、内容に沿ってかなり意訳した訳者さんの気持ちもよくわかるのですが、読み終わってみると、まさに「音楽の物語」だったよなあ、と納得する、素敵な本なのです。

本田聖嗣
1